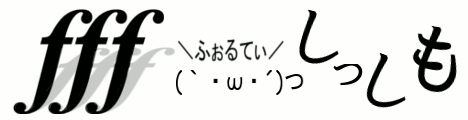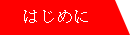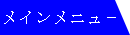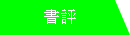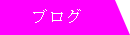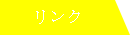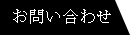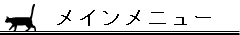文語体と口語体
- 厳密な意味での違い
- 皆さんは文語体と口語体を、書き言葉と話し言葉の違いであると解釈していませんか? もちろん、それも間違いではないのですが、本当は深い意味と事情があります。
- 「だ・である」などの、要はレポートや企画書などに使う「常体」=「文語体」という考えは、 古典の授業が苦手だった証拠かもしれません。(kaseがそうです)
- 文語と口語
- 結論から言うと、口語とはいわゆる現代語の事であり、対して文語は大日本帝国憲法などに代表される、 古典語で書かれた文章の事です。ちなみになぜ「文章」限定なのかは、歴史を見るとわかります。
- 今は昔
- もともと平安時代には、書き言葉と話し言葉でほとんど違いはなかったそうです。 古典の日本語は、いわゆる漢文の訓読の様な難解な文章です。(現代人にとっては)
- ですが時代が進むにつれて、話し言葉はどんどん進化していき、江戸時代に使われていた口語と現代語では、 ほとんど大差が無いと言われています。
- それが書き言葉(文語)の方は、時代が変わっても大きな変化はありませんでした。 そうして両者が別々に歩を進めた結果、江戸時代後期には文語と口語で全く違った言葉となってしまいました。
- 言文一致とは
- 明治になって、二葉亭四迷や山田美妙ら文学者を中心に、書き言葉(文語、古典語) を話し言葉と統一しようとする試みが始まります。それ以前、江戸時代においても、 すでに口語で書かれた書物が残っているそうなので、世間的には「もういいでしょう?」 という雰囲気があったのかもしれません。
- こうして言文一致運動が起こって、今現在と同じく、文章を書く際も口語体になったのです。 つまり「口語文」は現代文の事であり、決して話し言葉=口語ではありません。
常体について調べているうちに偶然学んだことなので、もしかしたら間違っている部分があるかもしれないので、 ここからの内容については要注意。
言文一致運動
これを勘違いしていたのはkaseだけだったのでしょうか。正直、古典・漢文は苦手教科でしたから、 上記が一般常識だったら恥ずかしい限りです…