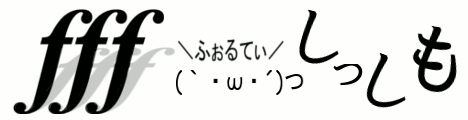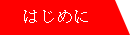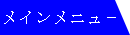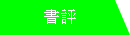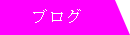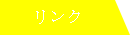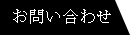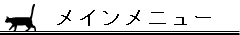句読点の基礎
内容が長い、ミステリーは嫌いだ。
上記の文章を見て、どう読み取りますか? 「内容が長いミステリー」が嫌いなのか、 「内容が長いから」ミステリーが嫌いなのか、どっちにも取れると思います。 読点の場所だけで、文章が伝わりにくいものになってしまう例です。
- 句点「。」の使い方
- 句点のルールは基本的に1つ、文の終わりに入れます。←コレ
- ただ、わかりにくいのは括弧で括られた文章です。
- (例)彼はこう言った。「だが、断る。」
- ジョジョネタですみません。この文章だと、「だが、断る」と書くバリエーションもありますよね。 小学校などの基礎では、カギ括弧でもマルを付けると習ったはずです。しかし一般的には「」には句点をつけない 場合が多いようです。特に会話文では句点を省きます。
- しかし、通常の()では基本的に句点を付けます。(このように付けます。)(もしくはこの様に付けます)。
- それから!や?を語尾に付ける場合は、句点はつけません。
- 読点「、」の使い方
- 文節と文節の間に入れるのが読点ですが、全ての節間に入れていたら非常に読みにくい文章になります。 ではどこに入れるのか?
- (例)綺麗な液晶のテレビだ。
- 上記の文章は、最初の例文と同じく、読点を入れる場所で文の意図が変わる文章です。 「綺麗な」の後に読点を入れると、「液晶のテレビ」が綺麗という意味になります。でも「液晶の」で読点を入れると、 液晶が綺麗という意味になりますね。
- 基本的に、修飾語や修飾部がキッチリと意味の通るように読点を付ければいいのです。が、 残念なことにコレと言った決まりはないみたいです。
- それから単語の並列にも使います。
- (例)果物はリンゴ、ミカン、イチゴ等です。
- 決まりが無いものを使えと言うのに、好き勝手に読点を入れれば意味が通らない、 句点より扱いが悪いですね。
句読点のコツ
主語が一番最初に来る文章は、主語の後に読点を付けると、意味的にも見栄え的にもバッチリです。
(例)私は、生まれてこのかた新聞を読んだことが無い。
句読点の付け方は、基本的に書く人の自由です。本を読んでると、独特の用法をする著者も居ます。 気をつけるのは、長ければ長いほど1つの文で使い方を統一する事です。あっちでは括弧に句点が入っているのに、 こっちでは使われていない、となると、違和感と読みにくさが出てきてしまいます。